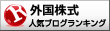こんにちは!
ゴローです。
以前から気になっていた本をついに購入しました。
2018年中には読まなければ・・・と思っていたのですが、
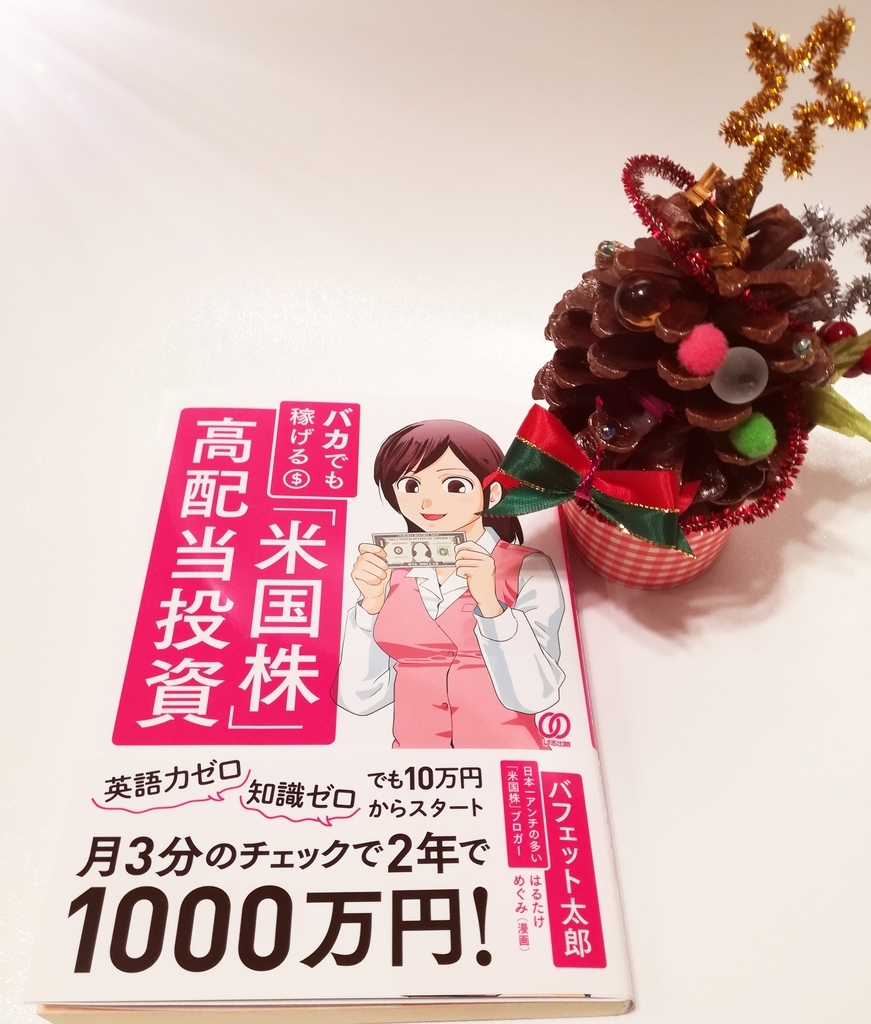
そうです。
バフェット太郎さんの『バカでも稼げる「米国株」高配当投資』です。
正直なところ、ゴローがブログを始めたのはバフェット太郎さんのブログが面白かったこともあったからです。
「好きなことをブログに書けるのか」というところから始まりました。
ちょっと言葉遣いが・・・なところもありますが、それも含めてバフェット太郎さんのブログであり、魅力です。
概ね1日に2回も更新していて、「どうやって時間をつくって記事を書いてるのかな」と思ったりしてます。
内容も、さすがに100冊以上、投資に関する本を読んでいるだけあって、詳しいですしね。
何より、バフェット太郎さんには「実績」がありますから。
説得力があります。
書籍の内容も、初心者の方にでも十分にわかりやすく書かれていて、知識の深さと広さを感じました。あとは経験値なんでしょうね。
職場でもそうですが、新入社員や配属されて間もない人に仕事を「わかりやすく」教えるって大変なんですよ。
その業務について「完全に」わかっていないと、教えられる側の「なぜ?」にうまく回答できなかったりします。
でもこの本は、そこのところがうまく説明されていて、過去データも参照しつつ、その「なぜ?」に回答してくれます。
なぜ米国株式投資なのか?
なぜ日本株ではダメなのか?
など、投資を始める方にとっては最初に抱く疑問に答えてくれるのです。
●分析能力で素人はプロに勝てない。しかしプロでも市場平均には勝てない
これはゴローが実感していることです。
ゴローは証券会社のレポートやアナリシスを読んでいますが、情報量でも、情報を読み込み、分析する能力においても、とてもではありませんが勝てる気がしません。
そんな状態でゴローは株式投資をしているわけですが、唯一勝てる見込みがあるのが、「プロは一定割合下げたら、いかなる理由があろうと売却しなければならない」、つまり損切りしなければならないところです。
個人投資家は本当の意味で、バフェットではありませんが「永久に」購入した株式を保有することができます。
ですからゴローは、暴落し「投げ売り」されている株式で、「回復しそうな見込みのあるもの」を購入しているのです。
つまりゴローは、株価の下値リスクが低い、暴落銘柄を購入するようにしています。
それもひとつのリスク回避の投資手法ですが、これは「さらなる下落リスク」を内包しています。
要するに、「リスクを回避したつもりが、自ら最悪のリスクに突っ込んでいく」可能性も十分にあるのです。
買った後さらに暴落するとか・・・
そして、そんなリスキーな方法よりももっと安全な方法が、・・・この本には書かれています。
しかも、リスクを下げて、利益も上げられるのであれば、それに越したことはないと思います。
それは「読んでからのお楽しみ」、というところでしょうか。
●読んでよかったなと思うこと
バフェット太郎さんの本を読んで個人的に「良かったな」と思ったのは、
「景気循環別のセクター投資の考え方」です。
景気の「回復期」「好況期」「後退期」「不況期」の4つの時期のセクター投資の考え方がとても勉強になりました。
ゴローはそんなこと考えずに投資していたので、ちょっと恥ずかしいなと思ってしまいました(汗
これならセクターごとに循環するマーケットの投資ポジションの移動も、自分のポートフォリオ内に含まれることになるので、どこかが下げればどこかが上がる、というサイクルを自分のポートフォリオ内につくることができます。
●こんな方におすすめ
「投資なんてしたことないけど、これから始めてみようと思っている方」はもちろん、自分で経済ニュースなどをチェックしていて、PERやPBR、PCFRなどの指標が意味するところを理解し、自分で銘柄分析までしてしまうような中級・上級者の方にもオススメです。
なぜかって?
それは、読んでみてわかることなのですが、これまで投資に関する専門書をたくさん読んできた方もたくさんいらっしゃると思うのですが、専門書はやはり専門書です。
1冊が分厚く、基本的には1つの投資理論に基づいて書かれています。
VaR(バリューアットリスク)やモダンポートフォリオ理論などがわかりやすい例でしょうか。
バフェット太郎さんの本は、それら100冊以上の投資本の「エッセンス」がうまくまとめられていて、バフェット太郎さんの具体的な「投資スタイル」にまで昇華しています。
つまり、「本を読んだ後から行動に移すまでがわかりやすく書かれている」のです。
投資の最低金額しかり、どこに投資すればよいかしかり。
読んだ本をアタマの中でまとめる作業というのはなかなか時間もないと大変なのですが、そこがうまくまとめられているので、個人的には自分のアタマの中でも「まとめられていく」感じがして、好印象でした。
まだ手に取っていない方がいらっしゃれば、ぜひ手に取って読んでみてください。
Take the risk or Lose the chance.